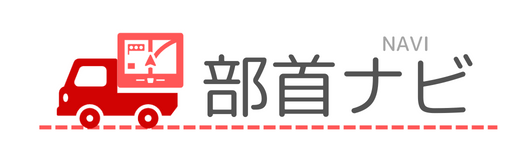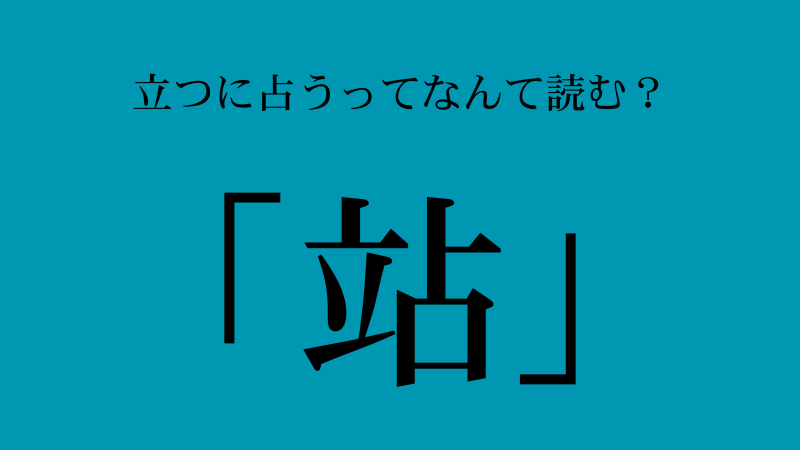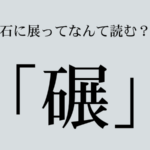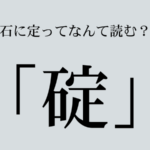ひなこ
「站(たつ・たん)」という漢字を見かけて、「どう読むの?」「どんな意味?」と疑問に思ったことはありませんか?
普段の日本語ではほとんど使われませんが、中国語では「駅」「立つ」を意味し、歴史や文化の中で大切な役割を担ってきました。
本記事では、「站」の読み方・意味・英訳・成り立ち・例文・歴史・名前や熟語での用例までを徹底解説します。検索ユーザーの「読みたい・知りたい・理解したい」に応える形でまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
「站」の読み方
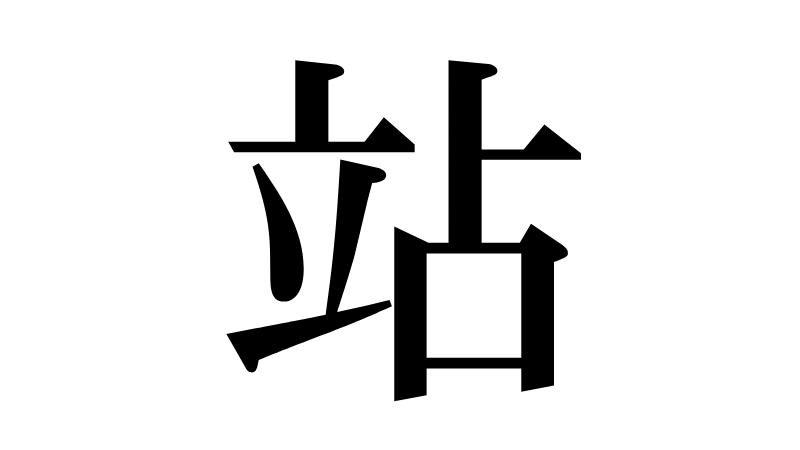
基本データ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 漢字 | 站 |
| 部首 | 立(たつ) |
| 音読み | タン |
| 訓読み | た(つ)※まれ |
| 人名読み | たち・たん |
👉 常用漢字外のため、一般的には人名や固有名詞で見られる程度です。
読み間違いに注意
- 「占(せん/うらなう)」と誤読しやすい
- 「湛(たん)」と混同される場合もある
- 中国語学習者は「站=zhàn」であり、「ジャン」ではなく「チャン」に近い発音と理解しましょう
漢字「站」の意味と英訳
意味
- 立つ、立ち止まる
- 駅・停留所(現代中国語での主要な意味)
- 拠点・基点
英訳(English Translation)
- stand
- station
- stop
👉 英語では「stand(立つ)」と「station(駅・拠点)」両方を表せるのがポイントです。
「站」を使った例文集
日常会話での例
- 我在车站等你。
(私は駅であなたを待っています。) - 请站起来。
(立ってください。)
ビジネス・公的文書での例
- 本公司在上海设立了服务站。
(当社は上海にサービス拠点を設立しました。) - 该项目需要在指定地点设站。
(このプロジェクトでは指定の場所に拠点を設ける必要があります。)
「站(立つに占う)」の成り立ち
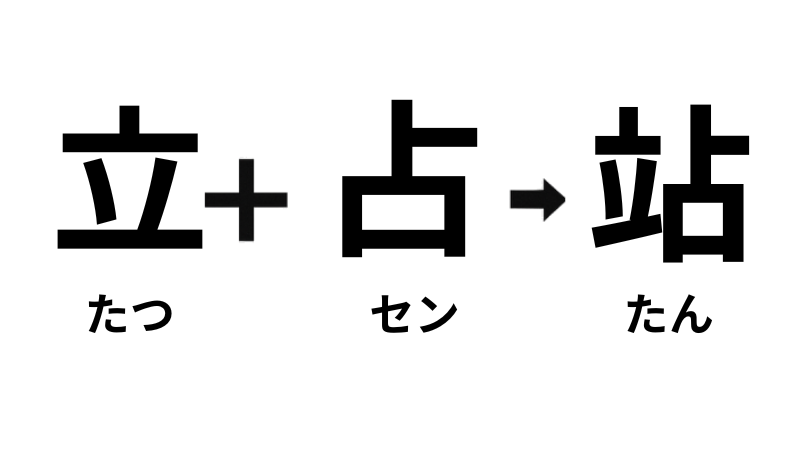
語源
- 「立」=立つ姿
- 「占」=位置を定める・しるしをつける
この組み合わせから「一定の場所に立つ」「拠点に立つ」という意味が生まれました。
「站」の歴史と文化的背景
古代中国での使用
秦代から漢代の文献に登場し、駅伝制度(驛站)で「站」が官設の休憩所・宿泊所を表すようになりました。
日本への伝来
日本に伝わりましたが、日常的な漢字としては定着せず、人名や地名で一部に残っています。
文学作品での例
唐代の詩文や宋代の詞に「驛站」として頻出。旅情や別れを表す文脈でよく使われます。
方言での使い方
- 北方方言 → 主に「駅」
- 南方方言 → 「立つ」の意味が強い
地域ごとにニュアンスが異なるのも特徴です。
站が入った名前や熟語
苗字・名字の例
- 站木(たちき)
- 站野(たちの)
下の名前の例
- 站太郎(たんたろう)
- 站子(たちこ)
熟語や関連語
- 驛站(えきたん/やくたん):駅伝の中継所
- 服务站(ふーうーざん):サービス拠点
- 加油站(かゆうざん):ガソリンスタンド
よくある質問(FAQ)
- Q日本語で「站」を使いますか?
- A
一般的な文章では使われませんが、人名・固有名詞では見られます。
- Q中国語ではどういう意味?
- A
主に「駅」「停留所」「立つ」を意味します。
- Q「站」と「站台」の違いは?
- A
「站」=駅そのもの、「站台」=駅のプラットフォーム。
まとめ(要点整理)
- 「站」は「立つ」「駅」「拠点」を意味する漢字
- 日本語ではほとんど使われず、人名・地名などに限定的
- 中国語では日常的に「駅・停留所」を意味する重要語
- 成り立ちは「立」+「占」で、拠点に立つことを表現
- 歴史的には駅伝制度に関連し、文化的な背景も豊か
👉 「站」を理解することで、漢字の成り立ちや中国語の奥深さに触れることができます。学習者や研究者にとっても知っておきたい一字です。