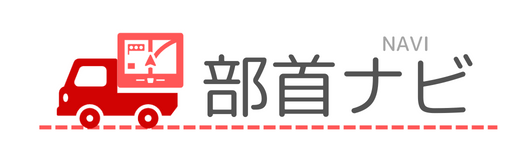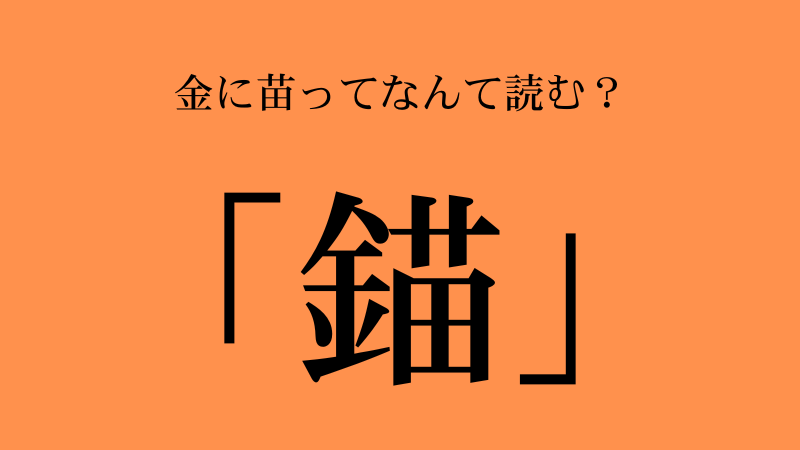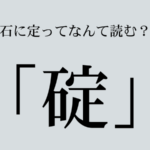「金へんに苗」と書く漢字、見たことはあるけれど読めない——そんな人は多いのではないでしょうか。
この漢字「錨(いかり)」は、船を固定する“アンカー”を意味します。音読みは「ビョウ」、訓読みは「いかり」。
この記事では、「錨」の読み方・意味・使い方・成り立ち・文化的背景を網羅的に解説します。漢字の由来から歴史的な使われ方、名前や熟語まで詳しく知ることで、「金に苗」の正しい理解が深まるでしょう。
「錨」の読み方

「錨」の基本データ(縦並び表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 漢字 | 錨 |
| 部首 | 金(かねへん) |
| 総画数 | 16画 |
| 音読み | ビョウ、ミョウ |
| 訓読み | いかり |
| 人名読み | なし(表外漢字) |
| 意味 | 船を留めるための重り(アンカー) |
(出典:『漢字ペディア』日本漢字能力検定協会)
よくある読み間違いと注意点
「錨」は「碇(いかり)」と混同されがちです。どちらも“アンカー”を意味しますが、「錨」は金属製のいかり、「碇」は石を使った古いタイプを指すことが多いとされています。
また、「金に苗」と見て「かななえ」などと読むのは誤りです。
漢字「錨」の意味と英訳
意味
錨とは、船を海底や湖底に留めておくために沈める器具を指します。
語義的には「錠(しっかり留める)」と同じく、“留める・固定する”というニュアンスを持ちます。
英訳(English Translation)
英語では anchor(アンカー)と訳されます。
例:
- cast anchor(投錨する)
- weigh anchor(抜錨する)
「錨」を使った例文集
日常会話での使用例
- 船が港に入り、錨を下ろした。
- 嵐の前に錨をしっかり打つことが重要だ。
ビジネス・公的文書での使用例
- 「信頼を企業の錨として、変わらぬ価値を提供する。」
- 「長年の経験が組織の錨となっている。」
このように、比喩として「心の支え」「基盤」を表す場合にも使われます。
錨(金に苗)の成り立ち
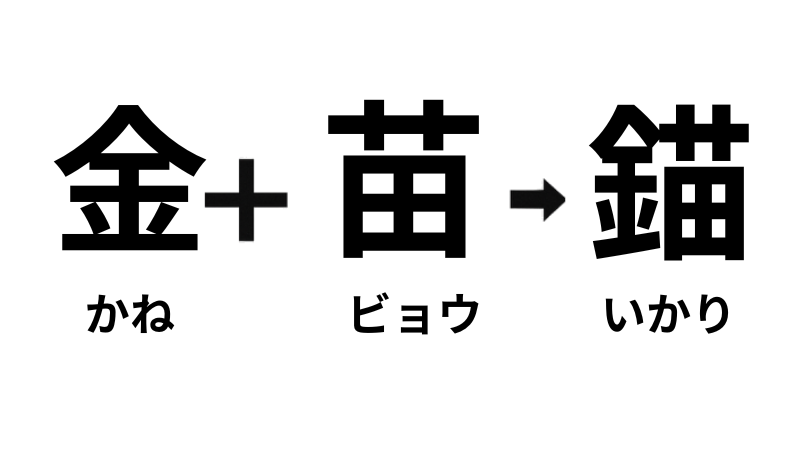
語源や成り立ち
「錨」は形声文字で、
「金(かねへん)」=金属を示す部首
「苗(びょう)」=音を表す部分
から構成されます。
すなわち「金属製の錘(おもり)」という意味を持つ漢字です(出典:『漢字ペディア』)。
「錨」の歴史と文化的背景

古代中国での使用
古代中国では「錨」は船具として使われていましたが、初期のいかりは石や木で作られており、「碇」という字が主に用いられていました。
日本への伝来と変化
日本では奈良時代以降、仏教伝来と海上貿易の発展とともに「碇」「錨」両方の文字が使われ始めました。明治期に西洋船が導入されると、鉄製アンカーを示す文字として「錨」が普及しました。
文学作品での使用例
夏目漱石『三四郎』や吉川英治『宮本武蔵』などの文中にも、「錨を上げる」「錨を下ろす」といった表現が登場します。
文学では、**「旅立ち」や「決意」**を象徴する比喩として使われます。
方言での使われ方
一部の漁村では、「いかり」を意味する言葉として「びょう」や「みょう」と発音される地域もあります(古音の名残)。
錨が入った名前や熟語は?
苗字・名字の例
非常に稀ですが、「錨田(いかりだ)」のような地名・名字が存在します(出典:日本姓名録データベース)。
下の名前の例
「錨」は人名用漢字に含まれないため、正式な戸籍名には使用できません。
ただし、芸名や雅号、ペンネームなどで用いられることがあります。
熟語や関連語の例
- 投錨(とうびょう):錨を下ろす
- 抜錨(ばつびょう):錨を上げる
- 起錨(きびょう):出航する
- 錨地(びょうち):停泊地
よくある質問(FAQ)
- Q「錨」と「碇」はどちらが正しいの?
- A
どちらも「いかり」を意味しますが、錨=金属製/碇=石製という区別が一般的です。
- Q人名に使える?
- A
「錨」は人名用漢字に含まれていません(法務省戸籍法施行規則より)。
まとめ(要点再確認)
- 「金に苗」と書いて「錨(いかり)」と読む
- 音読み「ビョウ」、訓読み「いかり」
- 意味は「船を固定するための重り=アンカー」
- 成り立ちは「金+苗」の形声文字
- 比喩的には「支え」「基盤」を象徴する
- 「碇」との違いは材質による区別